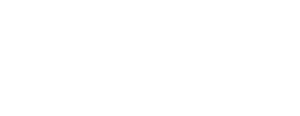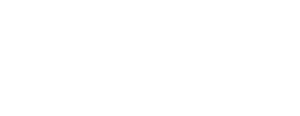相続税の申告
税理士の報酬は、税理士法により一定金額が決められていましたが、平成14年3月に廃止され自由化されました。このため、報酬は独自の規定に基づき、安価な報酬は十数万円から、高額な場合は数百万円と大きな幅があります。提供するサービス内容や遺産の総額、相続財産の種類等により報酬額は変動します。
税理士報酬は安価な方が良いものの、それだけを基準に税理士を選ぶのは好ましくありません。報酬が安価であっても、適正な評価・申告ができなければ相続税を多く納める結果となり、申告後の税務調査により追徴課税を受ける場合もあります。
一時的なコストだけでなく、総合的なトータルコストで税理士をお選びください。
贈与税の申告
一般的に「生前贈与をしておくと相続税が安くなる」と言われます。
生前に贈与が可能であれば、前もって財産の移転が終わるため、相続が起きた場合には相続税は安く済みます。
しかし、贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度があり、相続が発生した場合には「一定の贈与財産は相続財産として加算」され相続税の対象となるため注意が必要です。
これでは生前贈与には何のメリットも無いように思われますが、決してそのようなことはなく「いつ」「誰に対して」「どの財産」を贈与するのかが重要です。
特に、贈与税制度の選択によっても相続税は大きく変動するため、多角的な検討から最善のご提案をいたします。

不動産譲渡所得の申告
平成28年4月、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」が新設されました。
相続が発生すると、これまでの不動産本来の利用目的が失われることが多く、相続人にとっても維持コストは大きな負担となります。相続した不動産が未利用のまま塩漬けになるケースが社会問題化されたことを受け、「空き家を譲渡した場合の3000万円の特別控除」が新設されました。
特例の適用には一定の要件はありますが、特別控除の適用により「譲渡益3000万円までは無税」となる大きなメリットがあります。
ご注意いただきたいのは、特例には厳格な部分があり、要件の一つでも満たさない場合には特例の適用は無いため、細心の注意が必要です。
また、3000万円の特別控除以外にも譲渡所得の特例は数多くありますので、不動産譲渡の態様に応じた各特例についてご説明し、最も有利となる申告方法をご提案いたします。